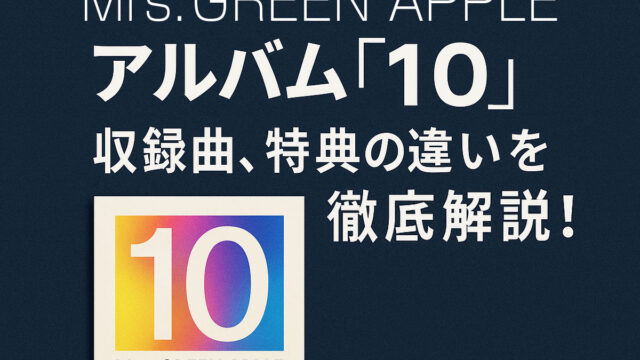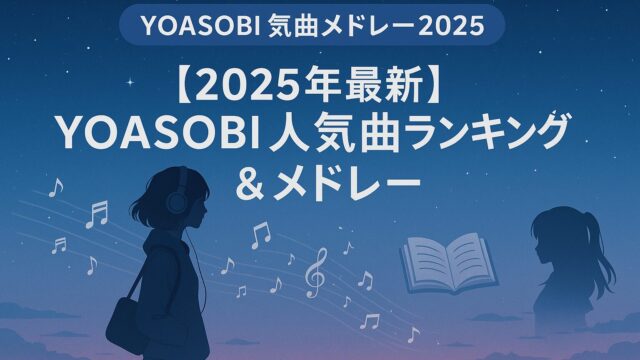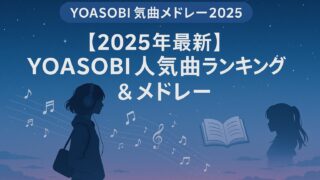「Vaundyって、結局なに者なんだろう?」
ジャンルの枠を軽々と越えながら、10代から30代まで幅広く支持される理由は何か──。
本記事では、セルフプロデュース・多様な音楽性・時代との共鳴という観点から、Vaundyの音楽がなぜ“広く届く”のかを読み解きます。
変わり続けることを肯定し、「ジャンル」ではなく「人間」に寄り添う音楽。その本質に迫ります。
はじめに:Vaundyの音楽は「一言で説明できない」から届く
初めて《怪獣の花唄》を聴いたとき、思わず「これ、誰?」と口に出た。
次に《不可幸力》を再生した瞬間、あまりの違いに「ほんとに同じ人?」と困惑した。
でも、どちらもたしかに“Vaundy”だった。
Vaundyというアーティストを一言で説明するのは、かなり難しい。
ロックのようで、ポップでもあり、時にR&Bやファンクのニュアンスもある。
そして、それらすべてが不思議なバランスで“自分のもの”になっている。
ジャンルを横断しているのに、どこか統一感がある。
それが、彼の音楽を聴いたときに感じる最大の特徴だ。
では、なぜそんなことが可能なのか?
なぜVaundyの音楽はジャンルを超え、しかも“広く届く”のか?
その問いには、「時代の流れ」と「人間の在り方」の両方から迫る必要がある。
本記事では、彼の音楽性に潜む仕組みと感情を読み解きながら、“ジャンルに縛られない時代における個の在り方”について考えてみたい。
きっとあなたの中にも、「変わり続けること」や「自分が決まらないこと」に、どこか不安を抱いた瞬間があるはずだ。
Vaundyの音楽は、そんな私たちに「そのままでいい」と語りかけてくれる。
だから彼の音楽は、“広く届く”のではなく、“深く沁みる”のだ。
Vaundyの音楽性を形作るもの
セルフプロデュースによる「音楽の自由度」
Vaundyの最大の特徴のひとつは、楽曲制作のほぼすべてを自らの手で行っているという点だ。
作詞・作曲・編曲にとどまらず、MVのディレクションやアートワークの統括まで、彼は“自分の世界”を一貫してコントロールしている。
これは、単に「多才」という言葉では片づけられない。
むしろ、自分の感情や世界観を“誰のフィルターも通さず”に表現できる、という意味での「自由」こそが、彼の音楽の芯になっている。
セルフプロデュースとは、単に「ひとりでやること」ではない。
それは、「どんなジャンルであっても、自分らしさを保てること」だ。
だから彼は、ある曲ではヒップホップ的なリズムを用い、またある曲ではエモーショナルなギターサウンドを響かせる。
表面的なジャンルの“模倣”ではなく、自分の中にある感情や景色を音に変換する装置として、ジャンルを使いこなしているのである。
ジャンルを“真似る”のではなく“意味で選ぶ”
たとえば《踊り子》にはシティポップやネオソウルの香りがあるし、《CHAINSAW BLOOD》にはロック×EDMのような強烈な攻撃性がある。
だが、そこに“様式美”へのリスペクトはあっても、ジャンルへの「忠誠心」はない。
むしろVaundyは、「どんな感情を届けたいか」によって、音の文法を選んでいる。
彼にとってジャンルとは、“目的”ではなく“手段”なのだ。
このようなスタンスは、「ジャンルレス」というよりも「ジャンルフル」と言うべきかもしれない。
すべてのジャンルが彼の“言語”になっていて、その日の感情に応じて、最適な言語を選んでいるようにも思える。
歌詞のテーマの多様性と人間の複雑さ
Vaundyの歌詞世界もまた、音楽と同様に多面的だ。
たとえば《怪獣の花唄》では、自分の衝動を抑えきれず爆発してしまう感情を描きながら、
《花占い》では、すれ違う想いと後悔の余韻を丁寧にすくい上げている。
《踊り子》には人生の虚しさと、同時に抗いきれない“踊り続ける本能”がにじんでいる。
これらの歌詞には、「一人の人間の中にいくつもの感情が共存している」という現実が、飾らず描かれている。
それゆえに、どんな曲であっても「これ、自分のことかもしれない」と感じてしまう。
Vaundyは、「音楽の形」だけでなく「人間のかたち」そのものが多様であることを、楽曲で証明している。
ジャンルの境界を曖昧にすること、それはつまり、
“人間の輪郭”そのものを柔らかく捉え直すことに他ならない。
ジャンルレスであることの「必然性」

本人の発言から見えるスタンス:「全部Vaundyだから」
Vaundyはこれまで多くのインタビューの中で、「ジャンルに興味がない」と明言している。
たとえば『MUSICA』の取材では、「この曲はR&Bっぽいと言われても、僕は“それが何かわからない”」と笑っていた。
彼にとって音楽とは、ラベル付けされるものではなく、自分の内側から湧き出る衝動のようなものなのだ。
実際、彼のアルバム『strobo』『replica』を聴いても、意図的にジャンルを“飛び越えて”いるわけではない。
むしろ、それぞれの楽曲が自然とバラバラな形を取っているのに、「全部Vaundy」としか言いようがない統一感がある。
それはつまり、Vaundyにとっての“ジャンル”とは、結果的に付けられる「外側からの視点」にすぎないということだ。
音楽の文法よりも「感情」を軸にする姿勢
ジャンルとは本来、音楽的文法──コード進行、ビート、音色の傾向──を指す。
だがVaundyは、そうした“型”よりも、そのとき自分が伝えたい感情や空気感を第一にして曲を組み立てている。
《benefits》の疾走感、《Tokimeki》の多幸感、《裸の勇者》の切迫感──すべて異なるが、それぞれに“心の動き”がある。
このスタンスが、リスナーの“今の気分”にフィットする理由だ。
「この曲、ジャンル的に好きだから」ではなく、「今の自分に、ちょうど必要だったから」。
それはまさに、感情起点の音楽であるという証しでもある。
“多才”ではなく“多面的”であるということ
「Vaundyは天才」「Vaundyは多才」──そんな言葉がよくSNSでも飛び交う。
もちろん彼のスキルセットは圧倒的だが、実はもっと本質的なのは、“多面的”であるということだ。
これは、「なんでもできる」のではなく、「一人の人間の中に、いろんな自分がいる」という感覚に近い。
Vaundyの音楽は、外から見た“スペックの高さ”ではなく、内側にある“揺らぎ”や“矛盾”を正直に受け入れているからこそ、ジャンルレスになっていく。
ジャンルを超えることは、目指すべきゴールではない。
むしろそれは、「自分の中にある複数の視点」を無理に統一しようとしない生き方の表れだ。
Vaundyの音楽にジャンルがないのは、それが“人間らしい”からなのだ。
リスナーが「Vaundyらしさ」を感じる理由

ジャンルを超えても“共通する体温”がある
《踊り子》と《CHAINSAW BLOOD》を並べたとき、ジャンル的には正反対だ。
前者はメロウでグルーヴィー、後者は攻撃的でサウンドの密度も高い。
だが、どちらにも共通して流れている“Vaundyらしさ”がある。
それは、楽曲全体に宿る「体温のようなもの」だ。
Vaundyの曲には、どこか人肌のような質感がある。
それは、過剰なエフェクト処理を避けたボーカルの空気感だったり、
リズムの“揺れ”を意図的に残したビートメイクだったりする。
完璧を求めすぎず、少し不安定で、でも温かい。
この“余白”が、ジャンルを越えても「同じ人が作っている」と感じさせてくれる。
声とメロディラインにある親密な距離感
Vaundyの歌声は、技巧的に飛び抜けているわけではない。
でも、「あの声じゃないと成立しない」と感じさせる磁力がある。
ハスキーな低音から高音域のファルセットまで、柔軟に行き来するその声は、
どんなジャンルに置かれても“聴き手との距離感”を見失わない。
また、彼のメロディラインはどこか口ずさみやすく、歌詞と旋律が寄り添うように流れている。
聴いていて自然に覚えてしまうのに、どこか切なさや影が残る。
その絶妙な“光と影のバランス”が、Vaundyという存在にしかない親密さを作っているのだ。
楽曲に潜む“人生の断片”──誰にでも当てはまる物語性
Vaundyの曲は、ときに恋愛、ときに自己肯定、ときに社会への問いを描いている。
だが、それらは「これは恋の曲」「これは応援ソング」といった型にはまらない。
むしろすべてが、“誰かの人生の途中”のような断片として描かれている。
それは、リスナーが自分自身の物語とリンクさせる余地を残しているということでもある。
たとえば、ある人にとって《花占い》は「別れの歌」かもしれないし、
別の人にとっては「まだ終わっていない気持ちを抱えたまま生きる歌」かもしれない。
この“解釈の余白”と“心の鏡”としての力こそが、Vaundyが広く届く理由の一つだ。
ジャンルを超えても、形式を変えても、
その奥にある“人間の物語”にこそ、Vaundyの音楽の核がある。
サブスク時代にフィットする音楽の在り方

プレイリスト時代における“曲単位の消費”
いま、音楽は「アーティスト単位」ではなく「曲単位」で聴かれる時代にある。
SpotifyやApple Musicでは、プレイリストやレコメンド機能によって、ジャンルもアーティストも横断的に楽曲が流通する。
この文脈で重要になるのは、「どんな曲でも、その瞬間の気分にフィットするか」という一点だ。
Vaundyの音楽は、まさにこのプレイリスト的文脈に極めて適応している。
ロック調の《裸の勇者》も、ミドルテンポの《恋風邪にのせて》も、
エレクトロな《Tokimeki》も、それぞれに異なる感情のスイッチを持っている。
リスナーは、その日の天気や気分によって曲を選ぶ。
そして、どんな曲でも“ちょうどいい”Vaundyが見つかる。
それが、「Vaundyがどこにでもいる」ような感覚を生んでいるのだ。
「多様であること」が評価される文化的背景
一昔前なら、「この人は何のジャンルの人?」という明確な立ち位置が求められていた。
だが、令和という時代においては、「一貫性」よりも「多面性」の方が、むしろ信頼につながるようになっている。
それは、社会全体が「一つの正解」を失っているからだ。
仕事も、恋愛も、価値観も、「これが正しい」と言い切れない時代。
だからこそ、いろんなジャンルを行き来できる人や、“定まらなさ”を肯定してくれる存在に、多くの人が惹かれる。
Vaundyはまさに、そうした“時代のムード”と共鳴しているアーティストだ。
ジャンルを超える彼の音楽は、「自分もいろんな顔を持っていていいんだ」と思わせてくれる。
それが、彼の音楽が“評価される”以上に“必要とされる”理由でもある。
Z世代の感性とVaundyのシンクロ性
Z世代の特徴としてよく挙げられるのは、「多様性への感受性の高さ」と「本音への敏感さ」だ。
SNSを日常的に使いこなす彼らは、表面的な演出よりも、その奥にある“人となり”や“本質”を見抜こうとする。
Vaundyは、決して多くを語らない。
けれど楽曲を通して、「こんな気持ち、わかるだろ?」と差し出す手の温度がある。
それが、Z世代が“共有しない共感”を感じられる空間を作っている。
リスナーが「これ、まさに自分だ」と言うのではなく、
「言葉にできないけど、これを聴いてる自分が好き」と思えるような音楽。
Vaundyは、その“自己感覚の拠りどころ”として機能しているのだ。
アルバム『replica』に見る“変化する個”の肯定

「本物」とは何かを問う構造
2023年にリリースされたVaundyの2ndアルバム『replica』は、まさに“アイデンティティ”をめぐる音楽的ドキュメントだった。
タイトルの「レプリカ(複製)」には、「本物らしさ」「自分らしさ」とは何かという問いが込められている。
この作品全体が、「コピーとオリジナル」「虚構とリアル」を行き来しながら、自分を探す旅のように構成されている。
収録曲のひとつ《そんなbitterな話》では、社会に対する苛立ちや不全感を描きながら、
《replica》では「どれがほんとの僕なの?」という問いを浮かび上がらせる。
そこにあるのは、変わり続けることへの肯定であり、“自分のままでいること”の不確かさすら、ひとつのリアルとして抱きしめる感覚だ。
自己が揺れ動くこと=Vaundyらしさ
一般的に、アーティストは“自分らしさ”を確立しようとする。
だがVaundyは、“自分らしさ”を定義しない。
むしろ、「揺れていること」そのものが、Vaundyであると言える。
あるときは強気でエッジィ、あるときは弱気でセンシティブ。
歌詞やサウンドの方向性が常に変化しているにもかかわらず、そこに共通するのは
「自分であり続けようともがいている」姿だ。
その葛藤ごと、音楽に焼き付けているからこそ、多くのリスナーが彼の曲に自分を重ねる。
令和的な“自己肯定”の新しい形
現代において“自己肯定感”という言葉はよく聞かれるが、それは「自信を持つこと」ではなく、
「定まらなくても、否定しないこと」というニュアンスを含むようになってきている。
『replica』でVaundyが描いたのは、まさにそうした“肯定のグラデーション”だ。
はっきりした答えは出さない。でも、その曖昧さこそが、今を生きる若者たちにとっての「リアル」であり、救いでもある。
「本物になれなくてもいい」
「今日の自分が昨日と違っていてもいい」
そんなメッセージが、彼の楽曲には息づいている。
変わっていくことを恐れずに、変わっていくことを歌う。それがVaundyの音楽だ。
まとめ:Vaundyの音楽は「時代」と「人間」を肯定している
ジャンルを超えること、それは簡単なようでいて難しい。
多くのアーティストが“新しいスタイル”に挑戦しても、どこか借り物のようになってしまうことは少なくない。
だがVaundyの場合、その変化は常に自然で、「本人のまま変化している」と感じられるのが不思議だ。
その理由を一言でまとめるなら、Vaundyの音楽は「自分という人間の複雑さ」を、そのまま音にしているからだ。
ジャンルを超えるとは、音楽的な器用さではない。
むしろ、「ひとりの人間の中に、いろんな顔があっていい」と認める視点があるかどうかが鍵になる。
そしてそれは、今という時代にとって必要なメッセージでもある。
ひとつの正解がない社会の中で、迷いながら、変わりながら、それでも「これが自分だ」と思える何か。
Vaundyの音楽は、その“揺れる自己”に寄り添い、肯定してくれる。
「決まらなくていい」
「いくつもの顔を持っていてもいい」
「その全部が、自分なんだ」
──そう語りかけるVaundyの音楽は、ジャンルを超えて、時代を超えて、人の心に届いていく。
それはもう、“ジャンルレス”ではなく、
“ヒューマン”そのものの音楽だと言っていいかもしれない。